私が住んでいる東京では外出自粛が続いており、早めの開花だった桜は先日の雪の日から、散りはじめてきています。毎年大きなお花見宴会をするタイプではないですが、ひっそりと少人数で御苑に出かけたりできないとなると寂しいものです。家の近くの幼稚園では毎年卒園式、入園式シーズンに花を咲かせる大きな桜の木があるのですが、世情とは関係なく今年も綺麗に花をつけ、可憐に散っています。どんなに周りが変化しても、どっしりと変わらない物があるというのは安心できるものです。
江戸時代のお花見はどんなもの?
もともと、お花見は1本の桜の老木の下で、一人でお酒を飲んだり、静かに歌を詠んだりして静かに楽しむ物だったそうです。それが、八代将軍吉宗が江戸城内で桜の苗木を育てて、隅田川の堤や飛鳥山、御殿山などの名所を作ったことで、現在のように「飲んで食べて騒ぐ」お花見になったと言うことです。近所に住む仲間と仮装して、どんちゃん騒ぎを楽しんだり、大道芸人や芸人もたくさん集まっていたそうです。
 |
| 東錦絵 国立国会図書館 |
今年は、ひっそりと楽しむのも良いかもしれませんね。お酒ではなく、水筒にお茶を入れて、お菓子とお茶で少しの時間立ち止まって眺めるのも粋なものです。
江戸時代のお花見は桜だけじゃなかった
小さな楽しみを見つけるのが上手な江戸人は梅見、藤見、かきつばたや菖蒲など、いろんな季節の花々が咲くと、家族や長屋の住人たちで出かけて花見を楽しんだようです。また花以外も秋になれば月見、虫の声聞きなど楽しいイベントが盛り沢山だったとか。今年は桜ではなく、コロナウィルスが収束したのち、季節の花々や虫の声を楽しみにするのも良いかもしれません。家の中から桜が見えるご家庭ならば、日向ぼっこをしながらお茶とお菓子で楽しむのもよいですね。
サーモス(THERMOS) (2018-08-21)
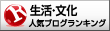



コメント
コメントを投稿